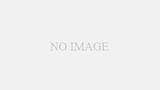Dentsu Diversity Lab や NHK の調査によると、日本における性的マイノリティ(LGBTQ)の割合は、現在およそ人口の7〜10%。この中でも、同性のみに惹かれるゲイやレズビアンは1〜3%ほどとされている。ここから先は、あくまで私の個人的な仮説である。
最近、明らかに「そっち系」の男性が増えてきた気がする。見た目も性格も中性的、いやむしろ女性的。メイクをしたり、全身脱毛したり、恋バナで盛り上がったり……「男らしさ」はどこへ行ったのか。「牙を抜かれたライオン」なんて言うと怒られるかもしれないが、明らかに時代が変わってきているのは事実だ。
もちろん、これは社会が少しずつ多様性を受け入れ始めたことの現れでもある。自己申告がしやすい環境が整った分、実態が表に出やすくなったのだろう。でも、それだけでは説明できない何かがあるような気がしてならない。
そこでふと思ったのだ。
もしかして、同性愛者の出現は「地球の自己防衛本能」なのでは?
増えすぎた人類と情欲の罪
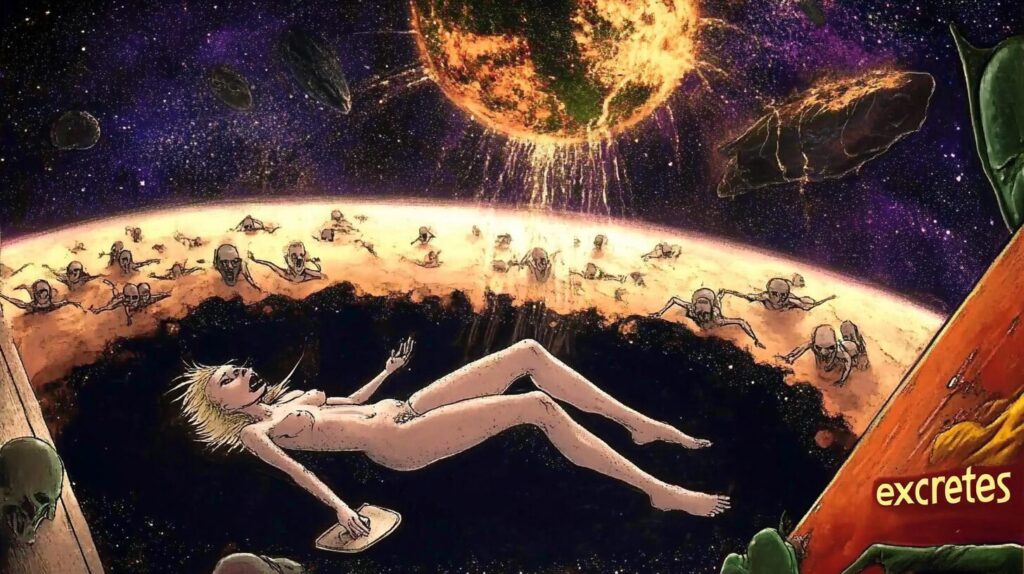
人類の人口は今や82億人を超え、今後40年で100億人に達すると言われている。医療の発達は寿命を延ばし、食糧技術も進歩した。その一方で、環境破壊、大気汚染、資源の枯渇といった「副作用」も深刻だ。
仮に地球を一つの生命体と見立てた場合、私たち人類はもはや“増えすぎた常在菌”、いや、いっそ“悪性腫瘍”のような存在なのかもしれない。そんな地球が「そろそろ限界」と感じたら、自然治癒力で何かしらの対応を始めてもおかしくない。
過去にもペスト、天然痘、コレラ、そして近年ではCOVID-19など、いわゆる“調整イベント”が歴史の節々で発生している。これらに対して人類はワクチンや抗生物質、文明の力で立ち向かってきた。だが、もし地球が「いやいや、もっと根本的に数を減らす方法があるんじゃない?」と考えたとしたら?
地球のホメオスタシス

動物は基本的に「増える」ようにできている。オスとメスが交わることで次世代が生まれる――これは生物としての本能だ。でも逆に言えば、「増えないようにする」にはこの仕組みをいじればいいわけだ。
つまり、オスがオスを好きになるようにすればいい。
「それ天才かよ!」と言いたくなるくらい、シンプルで効率的。ウイルスみたいに細胞分裂できるわけでもない人類は、性行為を経なければ増えない。ならば、「発情の方向性」をズラしてしまえばいいのだ。
これがもし、地球の中に組み込まれたホメオスタシス(恒常性維持)の一環だったとしたらどうだろうか。
ホモは地球を救う?
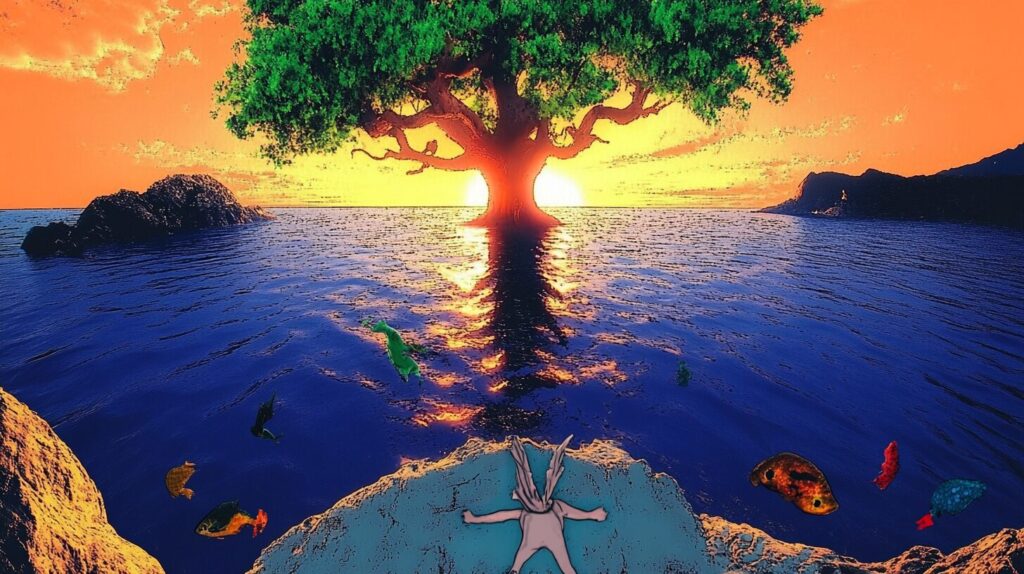
人類という“癌細胞”の増殖を防ぐために、地球が編み出した一つの手段。それが、**「増えない恋」**の仕組みだったとしたら……。
同性を好きになる。恋はするけど子は作らない。このスタイルが広がることで、地球の負担は少しずつ軽減されていく。これは実にスマートな解決策だ。病気でバッタバッタと死んでいくよりも、ずっと優しい減少策と言えるかもしれない。
もちろん、これは一つの仮説であって、同性愛が単に「地球の都合」だけで生まれるとは思っていない。でも、もしこの発想を「自然な多様性の一部」として受け入れられたら、性的マイノリティへの理解も少し違ったものになるのではないだろうか。
同性愛を社会問題としてのみ捉えるのではなく、地球という大きな生命体の“調整メカニズム”の一つだと考える――そんな視点があってもいい。これは、私たち人類が地球とどう共存していくべきかを考える上で、案外ヒントになる話なのかもしれない。
最後にひと言:
私自身、別にスピリチュアルでもなければ科学者でもない。ただ、こうやって地球と人間の関係をユーモアと少しの皮肉を込めて考えるのは、意外と面白い思考実験だと思っている。